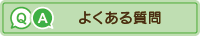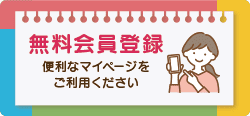ごっこ遊びとは?身につく力とおすすめの遊び方をご紹介!


おままごとや〇〇屋さんごっこなどのいわゆる「ごっこ遊び」は、子どもが好む普遍的な遊びの一つです。日本においては平安時代の貴族が始めて江戸時代には庶民に定着したと言われており、小さい頃にごっこ遊びを経験したという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ごっこ遊びとは何か、ごっこ遊びで身につく力、おすすめのごっこ遊びや遊ぶ時のポイントについて解説しています。ごっこ遊びが子どもに与える影響を押さえておくことで、子どもの力を伸ばしつつ楽しく遊ぶヒントになるでしょう。
ごっこ遊びとは?
ごっこ遊びとは、何かになりきったり役割を演じたりする遊びのことです。自分一人ですることもあれば、お友だちや保護者と一緒になって複数人で遊ぶこともあります。また、身の回りのものを小道具や衣装に見立てたり、物語を作ったりすることもあります。
一般的に、ごっこ遊びは2歳頃から小学校低学年頃まで行われると言われています。中でも、4〜5歳頃がピークにあたります。
ごっこ遊びには、大きく分けて2種類あります。1つはおままごとや〇〇屋さんごっこに代表される役割分担タイプ、もう1つはヒーローごっこやプリンセスごっこのようななりきりタイプです。
ごっこ遊びで身につく力には5つある
保育園や幼稚園、家庭にごっこ遊びを取り入れることで、子どもには様々な力が身につきます。今回は、想像力、協調力、表現力、観察力、社会力の5つをご紹介します。
想像力
ごっこ遊びは、子どもが頭の中で想像したイメージに沿ってキャラクターになりきる、あるいは役割を演じることで展開します。自分とは違う人物や独自のストーリーを想像して遊ぶことになるので、自然と想像力が養われると言えるでしょう。身の回りのおもちゃや折り紙などを使って必要な小道具や衣装を作る、見立てるといったこともあるため、想像力と同時に創造力も身につきます。
協調力
お友だちや保護者と一緒にごっこ遊びをする場合、自分の頭の中で考えたストーリーや展開、役割分担などを相手に伝えて共有することが大切です。お友だち同士で遊ぶのであれば、時には相手に役割を譲ったりやりとりを合わせたりするケースもあるでしょう。ごっこ遊びを行うことで、相手に自分の意図を伝えて協力して遊ぶために大切なコミュニケーション能力、協調性が育まれます。
表現力
前述したように、ごっこ遊びには役割分担タイプとなりきりタイプがあり、どちらの場合もその役割やキャラクターらしい喋り方やポーズ、ストーリーに応じた表情や行動がキーになります。ごっこ遊びの際になりきったり演じたりすることで、頭の中のイメージを表現する力が磨かれるのです。また、相手に伝わらないとごっこ遊びがスムーズに進行しないので、どのように表現したらイメージの共有が上手くいくのか、子ども自身が考える訓練にもなります。
観察力
表現力の項目でお伝えしたように、ごっこ遊びでは表現力が大切です。そして、頭の中のイメージを表現するためには普段から周囲を観察しておく必要があります。どんな喋り方やポーズをすればなりきることができるのか、どんな台詞や動きがシーンに適しているのか、どんな感情の時にどんな表情になるのかを知らなければ、遊びの中で表現できないからです。楽しくなりきったり演じたりするために、子どもは自然と周囲を観察し、記憶するようになるでしょう。
社会力
社会力は、特に役割分担タイプのごっこ遊びで培われる能力です。例えばケーキ屋さんごっこをする場合、店員役は「いらっしゃいませ」や「ありがとうございました」といった接客の言葉や、「お会計は〇〇円です」といった丁寧な言葉を使います。お客さん役は、欲しいケーキを店員役に伝えてお金を払い、ケーキを受け取るという流れに沿って、「これとこれを1つずつください」「箱に入れてください」などのやり取りを行います。大人のやり取りを真似ることで、社会の一員として暮らしていくための社会力を身につけることができるのです。
おすすめのごっこ遊び
子どもの想像力次第で自由に生みだせるのがごっこ遊びの魅力でもありますが、その中でも定番かつ子どもの力を伸ばせるものを以下にご紹介します。
おままごと

おままごとは、家庭における大人の暮らしを真似るごっこ遊びです。お父さんやお母さん、お兄ちゃんやお姉ちゃんといった家族の役を各々に割り振り、家族の会話や家事を真似て楽しみます。それぞれの家族が普段どのような喋り方や行動をしていたか、どうすればなりきれるか、観察力と表現力が身につくごっこ遊びです。
おままごとをする際の小道具は、身の回りのものを利用して作ってみてください。例えば、お料理をするお母さんの小道具であれば、牛乳パックや厚紙で包丁やまな板、お菓子の空き容器で食器や鍋、折り紙で野菜などが作れます。子どもと一緒に作ることで、想像力と創造力を伸ばすことができるでしょう。
お店屋さんごっこ

お店屋さんごっこは、店員役とお客さん役に分かれてそれぞれの役割を演じる遊びです。どんなお店を選ぶかにもよりますが、基本的にはお客さん役は商品を選んでお金を払い、店員役は接客やレジ精算、商品陳列や呼び込みなどの仕事を行います。大人の社会活動を疑似体験することで、社会力が身につきます。店員役とお客さん役でやりとりを行うことで、協調性も鍛えられます。
お店屋さんごっこに使う小道具には、商品や買い物かご、値札やレジ、お金やお財布などがあります。お店の種類によっては、ケーキやパン、お花やアクセサリーといった商品を用意するのもおすすめです。いずれも、段ボールや厚紙、折り紙などを使って作れるので、子供と一緒に作って想像力と創造力を伸ばすことができます。
なりきり遊び

なりきり遊びは、子どもが好きだったり憧れていたりする誰かや何かになりきる遊びです。なりきる対象は、ヒーローやプリンセス、アニメのキャラクターやアイドル、動物や電車、魔法使いや忍者など、様々なものがあります。台詞や動きを真似するために、観察力と表現力が磨かれます。
また、なりきり遊びには衣装や持ち物が欠かせません。例えば、魔法使いであれば黒いビニール袋を使ってローブを、色画用紙を使ってとんがり帽子を作って身につけるとぐっと雰囲気が出ます。新聞紙を棒状に丸めた杖を振り、魔法を使う表現に使いましょう。
遊ぶ時のポイント!
最後に、子どもとごっこ遊びをする際に注意したいポイントを押さえておきましょう。
まずは、子どもの想像したイメージに寄り添うことが大切です。子どもの発想は突飛だったり矛盾があったりすることもありますが、大人の考えで否定してしまうと想像力が伸びません。子どもが作り出す物語に乗り、展開に詰まることがあればやりとりの中でヒントを出してさりげなくサポートしてください。
加えて、子どもと一緒に大人も楽しむことを心がけましょう。子どもと世界観を共有して一緒に遊んでくれる大人の存在は、子どもの安心感や自信を生み、遊びを通じてそれぞれの能力を伸ばすことにも繋がります。
まとめ
ごっこ遊びの概要やごっこ遊びで身につく力、おすすめのごっこ遊びや遊ぶ時のポイントをご紹介しました。
ごっこ遊びは子どもの遊びとしてポピュラーで身近なものですが、遊びの一言では片付けられない効果をもたらしてくれます。子どものイメージを尊重して見守り、大人も楽しんで一緒に遊ぶことで、観察力や表現力、社会力といった子どもの力を伸ばすことができるでしょう。
また、ごっこ遊びをする際は、子どもと一緒に小道具や衣装を作るのもおすすめです。作る過程を楽しめるのはもちろんのこと、想像力や創造力を育む効果も期待できます。