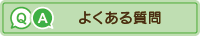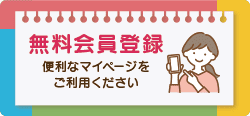七五三のお祝いは何をする?子どもの成長を祈る方法を紹介

七五三は、子どもの成長を祈る特別な伝統行事であり、そのお祝いとして神社参拝や写真撮影、食事会などがよく行われています。
準備を進める前に、七五三の由来や年齢ごとのお祝いの意味を知っておきたい親御さんもいることでしょう。この記事では、七五三の由来やお祝いの方法やポイントを紹介します。兄妹姉妹がいる場合の祝い方についても解説しますので、参考にしてみてください。
七五三の由来とは?なぜ11月15日なの?
七五三は子どもの成長を祈る伝統的な行事です。おもに3歳の男の子と女の子、5歳の男の子、7歳の女の子の成長を祈ります。
昔は今よりも衛生環境がよくなかったこともあり、7歳ごろまで順調に育つのが難しいといわれていた時期もありました。このため、7歳までの奇数年齢の際に、成長を願う儀式が行われた経緯があります。
奇数の年齢で祝う理由の一つに、中国の暦学の影響があります。暦学が日本に伝わる際、奇数は陽(縁起が良い)とされ、たとえば、3歳で言葉を理解し、5歳で知恵がつき、7歳で乳歯が生え替わる年齢といったように成長における節目と重ねられました。この影響もあり、この時期にお祝いをする習慣が生まれたようです。
七五三は毎年11月15日に行われるのが通例とされていますが、その由来については徳川将軍家にまつわるものや、収穫と感謝の儀式と関連するものなど、様々な説が伝えられています。
3歳・5歳・7歳の年齢でお祝いする理由は?
奇数の年齢時にお祝いする意味については紹介したとおりですが、各年齢のお祝いの由来について、もう少し詳しく解説します。
3歳の時に行う理由は?【男の子・女の子】
3歳のお祝いは春を迎える頃に行われる儀式であり、由来は 「髪置きの儀」にさかのぼります。3歳の儀式は男の子と女の子の両方に関係しています。
平安時代には、男の子も女の子も生後7日目に生まれたての髪を剃り、3歳まで坊主頭で育てる風習がありました。その当時は、頭髪を剃ることで頭部を清潔に保ちやすくなり、病気を予防する効果があるといわれていました。
「髪置きの儀」は長寿を祈願するために行われ、儀式の一部として、白髪を真似した白い糸や綿でできた白髪が子どもの頭上に置かれたといわれます。3歳の男の子と女の子の成長を祈るこの儀式は、昔からの伝統を継承しつつ、現代でも子どもたちの幸福を祈る特別な日として親しまれています。
5歳の時に行う理由は?【男の子】
5歳のお祝いについては男の子対象の儀式となっており、 「袴着(はかまぎ)の儀」に由来しています。袴着の儀とは、平安時代に5歳から7歳の間でおこなわれていたもので、当時の正装である袴を初めて身に着ける儀式でした。
初めの頃は男女ともに行われていましたが、江戸時代になると男の子のみの形式に代わります。この儀式は男の子が少年の仲間入りを果たし、羽織袴を身につけることを象徴的に示すものです。
現在の七五三には見られない儀式もありました。特定の手順があり、男の子は縁起が良いとされる左足を先に袴に通し、冠をかぶりました。さらに碁盤の上に立ち、四方の神に向けて祈りを捧げたといわれています。この儀式は、勝利と繁栄を願う意味も込められていました。
昔も今も、男の子の成長と成功を祈る重要な儀式であることは変わらないと考えられます。
7歳の時に行う理由は?【女の子】
7歳のお祝いの場合、女の子に関連した儀式として 「帯解(おびとき)の儀」がおこなわれます。この儀式は、鎌倉時代からおこなわれており、着物を着る際に使われていた付け紐を外し、帯を初めて締める成長の儀式です。
初めは「帯解の儀」は男女ともに9歳で行われていましたが、江戸時代になると儀式に変更が加えられます。つまり、男児は5歳での「袴着の儀」、女児は7歳で「帯解の儀」をおこなう形に変わります。変更によって儀式が区別され、さらに7歳が女の子の成長を祈る特別な時期として認識されるようになりました。
七五三でのお祝い方法3選
七五三では、神社への参拝や記念撮影、食事会などが行われます。各催しについて詳しく解説します。実際に計画を立てる際の参考にしてみてください。
神社への参拝を行う

混雑を避けるためには、予約の早さが重要です。予約は通常、七五三の祝日の前後や週末に混雑することが予想されるため、8月ごろから9月初めごろに予約を入れたほうが良いでしょう。
両家の祖父母を招く場合は、全員のスケジュールを調整しなければなりません。最近では、日程について柔軟な対応をする家庭も多く、混雑期を外して9月や10月、場合によっては12月に入って参拝をおこなう場合もあります。
また、参拝のみ、ご祈祷をお願いするかによっても、当日の流れや所要時間が異なります。ご家族と相談しながら、当日の内容や時間、神社に納める初穂料、駐車場の有無なども確認することが必要です。ぎりぎりになって慌てないよう、ゆとりをもって参拝の準備を整えましょう。
記念撮影を予約する


記念撮影を行う場合、着物の着付けやヘアメイクを依頼するのもおすすめです。写真スタジオに専属の美容や着付けのスタッフが常駐する場合もありますが、個人の写真館で記念撮影をする際は、美容院などに予約を入れることも多いです。神社参拝の予約と合わせて、8月ごろから9月初めごろに予約を入れるとよいでしょう。
一部の神社では出張カメラマンを許可している場合もありますが、撮影の可否は神社によって異なるため事前確認が必要です。出張撮影を希望する場合は、許可手続きを行い、撮影日程を調整します。また、お子さんやご家族の具合を考慮して、参拝とは別日に記念撮影をすることも検討の余地に入ります。
いずれにしても、とっておきの一枚を撮影できるよう、ゆとりをもって関係する人々に連絡や予約をしていきましょう。
食事会に参加する
七五三の当日など、食事会と一緒に参拝や撮影も行う場合は、「参拝→撮影→食事会」の流れが一般的です。
食事会について、その方法や食事内容のポイントを解説します。
食事の準備方法
食事会を設定する場合は、下記の場所や方法を選べます。
- 料亭の個室やホテルレストラン:特別な料理と空間でお祝いをする
- 自宅:お手製の料理をふるまったり宅配サービスを利用したりする
- 一般的なレストランや食堂:子どもの好みに合う料理を楽しめる
家族が大勢で予算が限られている場合は、気兼ねなく利用できるレストランで食事を楽しむことも思い出の場面となるでしょう。
食事内容
七五三の際に食べるものは特に決まっていませんが、一般的に以下の料理が祝い事にふさわしいとされています。


- 尾頭付きの鯛:「目出鯛(めでたい)」とされる縁起物
- 赤飯:邪気を払い幸せを願う色合い
- ちらし寿司:見た目も華やか
- 紅白なます:お祝いの席の箸休め
- エビを使った料理:成長や長寿を祈る
以上の料理は、お祝いの席の料理によく出されるものですが、お子さんには少し口に合わないかもしれません。この場合は、子どもが好きな料理を用意するなどして柔軟に対応しましょう。
たとえば、エビフライは子どもにも人気があり、七五三の食事会にも適した料理です。その理由は、エビは長い髭と曲がった背中を持つ老人のような見た目をしており、長寿の象徴とされているためです。
七五三の食事会は、大切な時間を共有しながら家族の絆も深められる場です。心を込めて準備を整えて、当日は楽しい時間を過ごせるようにしましょう。
兄弟姉妹がいる場合のお祝いはどうする?
兄弟姉妹がいる場合の七五三のお祝いには、いくつかの選択肢があります。それぞれの方法は下記のとおりです。
- 同時に行う場合:イベントを一度で済ませやすい
- 別々に行う場合:年上の兄弟姉妹の着物をおさがりとして着せられる
- 同時に行う年齢差でなくてもまとめて行う場合もある
同時におこなう場合、たとえば2歳差や4歳差の兄弟姉妹では、お祝いのタイミングが合いやすくなります。また、3歳差であっても兄妹一人の七五三のお祝いに合わせて、まとめて行うこともあります。
以前は数え年でお祝いするのが一般的でしたが、現在は満年齢でのお祝いでも問題ないとされています。兄妹姉妹の七五三についても柔軟に対応し、家族が幸せなひとときを味わえる方法を見つけていきましょう。
まとめ
七五三は、日本文化の中で子どもの成長を祈る重要な行事です。3歳、5歳、7歳の各年齢でのお祝いの由来と意味について確認しつつ、神社への参拝や記念撮影、食事会についてもゆとりをもって予約することが重要です。
お祝いの仕方や兄妹姉妹がいる場合の方法についても、さまざまな選択肢があります。ご家族で相談しながら、七五三がお子さんや親御さん、ご家族の皆さんにとって、楽しいひとときになるよう計画的かつ柔軟に準備を進めていきましょう。