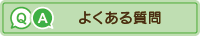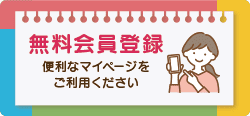保育園の運動会で披露する競技種目を年齢別に紹介!

保育園の運動会は、園児はもちろん、保護者の方々や保育士さんにとっても大きなイベントです。せっかく実施するなら楽しくて思い出に残る運動会にしたいと思いつつも、なかなかアイデアが浮かばずに悩むこともあるのではないでしょうか。
この記事では、保育園の運動会の狙いや幼稚園の運動会との違い、運動会におすすめのテーマや競技種目についてまとめました。具体的なアイデアをご紹介しているので、保育士の皆さんはぜひ参考にしてみてください。
保育園の運動会とは
まずは、保育園の運動会とはどういったものなのか、その狙いや目的、幼稚園の運動会との違いを押さえておきましょう。
【年齢別】保育園の運動会の狙い・目的
保育園には、幅広い年齢の子どもが通っています。そのため、乳児(0〜2歳)と幼児(3〜5歳)に分けて考え、それぞれに向けた狙い・目的を設定することをおすすめします。
乳児の場合は発達にばらつきが見られるので、それぞれの成長の過程を保護者と共に再確認することを重視しましょう。競技やお遊戯発表というよりは、這う、歩く、走るといった基本的な動きを通して体を動かす楽しさを感じてもらうのが目的です。保護者と一緒に動作を行ったり触れ合ったりすることで、信頼感を高めるという狙いもあります。
幼児の場合は、乳児よりも比較的体を動かすことに慣れています。保育園での遊びの中で身につけた体の動かし方を披露することを、運動会の狙いとして設定しましょう。ダンスやお遊戯といった表現の場を設けるのも効果的です。保育園における集団生活で培った協調性を、さらに伸ばすことができます。
保育園と幼稚園の運動会の違いについて
そもそも、保育園と幼稚園の運動会にはどういった違いがあるのでしょうか。
先ほども触れましたが、保育園には幅広い年齢の子どもが通っています。そのため、保育園の場合は午前中で運動会を終了して解散、幼稚園の場合は昼食を挟んで夕方近くまで実施することが多いようです。保育園には歩いたり走ったりが難しい乳児もいるため、運動会の会場は目が届きやすい体育館などの屋内になります。
また、保育園は同じ年齢の子どもは30人未満と少人数であることが多く、運動会の準備は保育士のみ、練習も短時間で適宜行います。対して幼稚園は一学年100人を超えることもあります。幼稚園教諭に加えて保護者が準備を行い、練習も毎日行われるのがポピュラーです。
| 内容 | 保育園 | 幼稚園 |
|---|---|---|
| 開催時間 | 午前中で終了 | 夕方まで実施 |
| 場所 | 体育館など屋内 | 園庭(グラウンド)など屋外 |
| 準備 | 保育士 | 保育士+保護者 |
| 人数 | 30人未満と少人数 | 100人近くの大人数 |
| 練習期間 | 短時間で適宜練習 | 毎日練習 |
※地域や園の環境などによっても異なるため、あくまで参考です。
運動会の開催時期と開催時間
運動会は、9〜11月頃の秋に開催されるケースが一般的です。10月の第二月曜日がスポーツの日として祝日に設定されているため、この連休を利用して運動会が開催されることもあります。ただ、秋は台風の影響を受けてしまう可能性があるため、気候が比較的安定している5〜6月頃に開催するケースも増えているようです。
開催時間は、先ほども触れたように保育園の場合は午前中のみで終了となるケースがほとんどです。
開催時期、開催時間は保育園によって異なりますので、行事予定をしっかり確認しておくことが大切です。
運動会のおすすめテーマ例
運動会の競技を決めるにあたって、テーマを設定することで統一感が生まれ、種目も決めやすくなります。以下に、おすすめのテーマ例をご紹介します。
オリンピックなどのスポーツイベントをテーマにする

スポーツの祭典であるオリンピックは、平和の祭典とも言われています。入退場のセレモニーや国旗、聖火といったモチーフも取り入れやすく、子どもたちがオリンピックや外国に興味を抱くきっかけにもなります。
例えば、国旗のようにそれぞれのクラスの旗を作って飾りつけたり、手持ち旗にして振ると賑やかで見栄えがします。オープニングセレモニーとして、聖火を模したアイテムや色とりどりの風船を持って入場するのもおすすめです。
また、運動会自体を「〇〇リンピック」と銘打ってパンフレットや看板を作っても、雰囲気が出て良いでしょう。最後にメダルを配布すると、運動会の記念にもなります。
生き物をモチーフにしたテーマにする

動物や魚などの生き物をテーマにしても、飾り付けや競技種目が決めやすくなります。子どもたちが好きなかわいい生き物や格好いい生き物、身近な生き物をモチーフにすることで、親しみやすくイメージしやすい運動会にすることができるでしょう。
例えば、「ペンギンの親子レース」や「ダンゴムシ競争」といった生き物をモチーフにした競技種目にすることで、子どもたちも保護者も楽しく参加できるのではないでしょうか。
【年齢別】おすすめの競技種目
それでは、実際におすすめの競技種目を年齢別にまとめました。実際の運動会のプログラムを決める際の参考にしてみてください。
乳児(0~2歳)におすすめの競技種目
・ダンゴムシ競争
ダンゴムシのように体を丸めたり這ったりしてゴールを目指します。まだ走ることが難しい年齢の子どもでも参加可能です。ダンボールでダンゴムシを模したキャタピラを作り、その中に入って進むのもおすすめです。
・コアラリレー
保護者が子どもをおんぶして、コアラの親子のような体勢でリレーを行います。子どもが保護者の元へたどり着くまでのパートと、おんぶしてからのパートに分けることで、子どもが体を動かす楽しさも味わうことができます。
・果物狩り競争
折り紙や新聞紙などで作った果物を用意しておき、保護者が持つかごに子どもと一緒に果物を入れていきます。果物は一箇所に固めておいてもいいですし、実際の果物狩りのように木や畑を模した箱を巡って回収するスタイルでも構いません。
・ペンギンの親子レース
保護者の足の甲の上に子どもが立ち、ペンギンのように歩いてゴールを目指します。自分でしっかりと歩ける子どもが対象ですが、保護者がしっかりと手を握って支えることで子どもにも安心感が生まれます。
・ダンボール自動車レース
ダンボールでカートを作り、中に入った子どもごと紐で引っ張って進みます。ダンボール製の車や紐が競技中に壊れないように、丈夫に作るようにしましょう。ダンボールに実際の車や新幹線のような色を塗ったり、可愛らしく装飾すると華やかになります。
幼児(3~5歳)におすすめの競技種目
・デカパンツ徒競走
大きなパンツを用意し、片足側に子どもが、もう片足側に保護者が入り、息を合わせて走ります。見た目は二人三脚と似ていますが、足首を固定するわけではないので難易度が低くなり、安全面でも安心です。
・玉入れ
運動会でお馴染みの玉入れも、3歳頃から楽しむことができます。アレンジも様々で、音楽が流れている間だけ玉を入れることができるもの、ダンスと玉入れを組み合わせたもの、妨害する役を配置するものなど、バリエーション豊かです。
・フラミンゴリレー
フラミンゴになりきって、片足でケンケンをしながらゴールを目指します。途中で両足をつける休憩ゾーンを設けるなど、子どもの発達に応じて工夫し、楽しめるようにしましょう。
・ダンス
音楽に合わせて踊るダンスは、観客も盛り上がる種目です。振り付けを工夫することで、難易度の調整を行います。衣装を揃えてもかわいいですが、手軽にポンポンや色手袋などを使っても十分に見栄えがします。
・ピンポン玉運び
おたまやスプーンの上にピンポン玉を乗せ、落とさないようにバランスをとりながら走ります。子どもの発達に合わせ、おたまやスプーンの大きさを変えて難易度を調整しましょう。
まとめ
保育園の運動会の狙いや幼稚園の運動会との違い、運動会におすすめのテーマと競技種目をご紹介しました。
保育園には様々な年齢の子どもがいるため、子どもたちが無理なく参加できて楽しめる競技種目を決めるには工夫をする必要があります。子どもも保護者も満足のいく運動会にするポイントは、子どもたちの発達に応じて難易度を上手く調整することです。この記事でご紹介した具体例などを参考に、競技を考えてみてください。